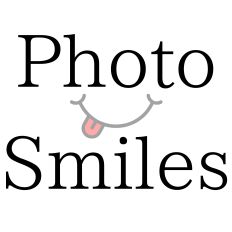七五三って「いつやるのが正解なんだろう?」と迷う方も多いですよね。
数え年?満年齢?秋にやらなきゃダメ?そんな疑問を、分かりやすく丁寧に解説していきます。
家族にぴったりな七五三のタイミングを見つけましょう♪

この記事を参考にして頂けたら幸いです。
- 職業:カメラマン/年間撮影300件以上
- 対応地域:関東近郊
- 撮影内容:ハレノヒ・家族写真など
- ✓数え年と満年齢の違い
- ✓お参りの時期の選び方
- ✓撮影に適したタイミング
- ✓家庭に合う七五三の決め方
\ 目次から気になる項目を選んでチェック /
七五三の年齢と数え年・満年齢の違い
七五三は本来「数え年」で行われてきましたが、現在は「満年齢」でお祝いする家庭も多く、神社もどちらにも対応しています。
3歳・5歳・7歳が基本ですが、兄弟姉妹で時期を合わせたり、成長に応じて調整するなど、柔軟な対応が一般的です。
数え年と満年齢どちらが正解?
七五三はもともと「数え年」で行うのが伝統的ですが、最近では「満年齢」でお祝いする家庭も多くなっています。
神社もどちらの年齢でも対応してくれるところが多いため、子どもの成長や家族の予定に合わせて柔軟に選ぶのが一般的です。
男の子・女の子の対象年齢
男の子は3歳と5歳、女の子は3歳と7歳でお祝いするのが基本です。
兄弟姉妹の兼ね合いや、お子さまの成長具合に応じて、1年ずらすケースもあります。大切なのは「無理のない年齢で祝う」ことです。
兄弟姉妹と年齢を合わせる場合
兄弟姉妹がいる場合、年齢の違いがあっても一緒に七五三を行う家庭も増えています。
一度の撮影・参拝で家族の記念をまとめられるため、スケジュールも立てやすく、祖父母を交えてのお祝いにも最適です。
七五三の写真を見てみる

















フォトスマイルズは、関東の神社・ハレの日を中心に撮影しています
年間約300件/関東の神社65社以上/会食対応15か所以上
お客様の口コミ
\ フォトスマイルズ写真集 /
七五三のお参りはいつが多い?
七五三のお参りは11月15日前後が最も一般的ですが、近年は混雑を避けて10月〜12月にずらす家庭も増えています。
休日は混み合うため、平日を選ぶと神社も落ち着いていておすすめ。家族の予定に合わせた柔軟な日程選びが主流です。
11月15日前後が基本
七五三はもともと旧暦の11月15日に行われていた行事で、今もこの前後に参拝する家庭が多く、最も混雑する時期です。
ただし、日付にこだわりすぎず、子どもや家族の体調・都合に合わせて日程を決める方が良い結果になります。
10月〜12月の傾向と分散化
混雑を避けたい方には、10月の早めのお参りや12月の後撮り参拝もおすすめです。
神社によってはご祈祷の対応が12月上旬まで可能なこともあるので、事前に確認しておくと安心です。
平日と休日どちらが人気?
多くの家庭では土日祝を選びますが、実は平日の方が神社も撮影も空いており、落ち着いてお参りできます。
仕事や学校との調整ができるなら、平日を選ぶことで写真にも余裕が生まれ、良い表情を残しやすくなります。
撮影におすすめの時期と曜日
七五三撮影は混雑する11月を避けて、10月の前撮りや12月の後撮りを選ぶ家庭が増えています。
特に午前中は子どもの機嫌も良く自然光がきれいなためおすすめ。平日は神社や撮影スポットが空いていて、落ち着いて撮影できます。
前撮りと後撮りの違い
七五三当日は何かと忙しく、子どもが疲れてしまうこともあります。
そのため、撮影だけは別日に行う「前撮り」や「後撮り」が主流になりつつあります。
10月の前撮りや、混雑を避けた12月の後撮りも人気です。
カメラマン予約の混雑時期
出張撮影やフォトスタジオは9月〜11月が繁忙期です。
特に人気の午前中や日曜はすぐに予約が埋まってしまうため、遅くとも1ヶ月前には予約するのが安心。
予約のタイミングが成功のカギになります。
午前と午後どちらがいい?
撮影は午前中が断然おすすめ。子どもの機嫌が良く、自然光も柔らかくて写真写りがキレイです。
午後は疲れや眠気が出てきたり、日差しが強すぎることもあるため、午前中を優先的に検討しましょう。
地域や家庭で異なる七五三の時期
七五三の時期は地域や家庭によってさまざま。
関東では11月15日前後が主流ですが、関西では10月に行うこともあります。祖父母の都合や兄弟の行事に合わせる家庭も多く、「みんなで集まりやすい日」を選ぶ柔軟な対応が増えています。
関東と関西で異なる風習
七五三の風習は地域によって異なり、関東では11月15日を中心に行われますが、関西では10月に済ませる家庭もあります。
また、地域の氏神様に参拝する文化や、地元の風習によって日程を調整するケースも見られます。
神社の混雑状況に合わせる
有名神社では土日祝にご祈祷予約が集中し、駐車場や受付に長蛇の列ができることも。
事前に神社の公式サイトで混雑状況やご祈祷のスケジュールを確認しておくと、当日慌てずスムーズに行動できます。
家庭の都合に合わせてOK
家族全員の予定が合う日を優先して日程を決めるのも十分アリです。
特に祖父母が遠方から来る場合や、兄弟姉妹の学校・習い事との調整がある家庭では、無理のないスケジュールで七五三を迎えることが大切です。
まとめ|七五三は「年齢と時期」が決め手
家族の笑顔があふれる七五三になりますように♪
家庭に合ったタイミングで
七五三の正解は家庭ごとに異なります。
年齢の考え方や参拝のタイミングは、伝統にとらわれすぎず「その子らしさ」や「家族の心地よさ」を大切にすることで、思い出深い一日になります。
撮影とお参りは分けてもOK
撮影とお参りを同日に詰め込むと、移動や着替えなどで大変になりがち。
近年は前撮り・後撮りでゆったり撮影を済ませる家庭が多くなっています。
当日はお参りに集中できるため、家族みんなが笑顔で過ごせます。
早めの検討と相談が安心
お参りも撮影も、人気の時期は早く埋まってしまいます。
特に秋の土日・大安・戌の日は予約が集中するので、夏のうちに神社や撮影の候補を家族で相談しておくと、スムーズに予定が組めます。
\ 関東神社に詳しい /
オンライン予約